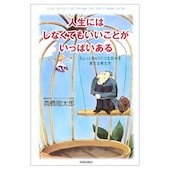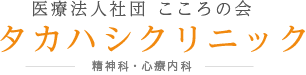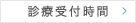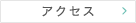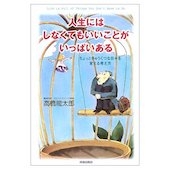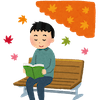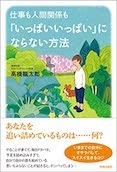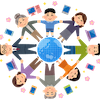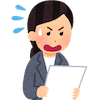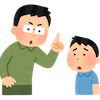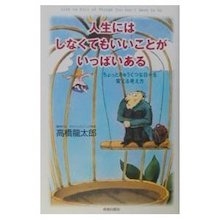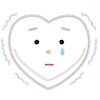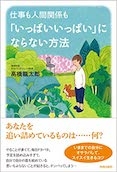つらくて、どうにもこうにもできないとき、楽しそうにしている人を見て「ああ、あの人はいいなあ」と思ったりすることがあるでしょう。
でも「毎日楽しくてしょうがない。私は生まれてきて良かった」なんていう人は、じつはいないのです。多くの人は、生きるために努力が必要だろうし、人生で起きる、いろんなことは、「苦しみの連続」とまでは思わないけれど、「楽しさではないものの連続」なのではないでしょうか。その中に、一つ二つ、何か光るのもとか、自分にとって楽しいものが見えたときに、その絵柄が全部「ドーン」とひっくり返って「生きててよかったなあ」って思えるのではないでしょうか。
なんだかんだ言いながら、あんまり楽しみのない人生だと思っていたのが、どこかで輝き始める。それは有り体に言えば、子どもが生まれたときのような、なにか大きな変化、あるいは小さいながら変化が積み重なって、全部が「コロッ」とひっくり返るようなことが人生には隠されているということです。考えてみてごらんなさい。毎日楽しいと思っている人はいつのまにかそれに慣れてしまい、毎日楽しいなんて思えなくなるのです。
そういうときのために常日頃心構えしておくことが私たちには必要なんです。そのときにそれを逃すと、なかなかまた出会うまでに何年もかかるという話になってしまうかもしれないし。ただ、そうなってしまうとあまりに悲しいですけれど。
ですから「生き続けるということ」の中にじつは、楽しさも含めた人生の何らかの真実が隠されている。これは、最初に分かっておいてもらいたいことかもしれません。
そうでないと、若い人が「二〇歳にして朽ちたり」というような感じで、二〇歳くらいで「もう人生面白くないスよ。もう生きててもしょうがないから、死んでもいいですか?」と言ったりするんですよね。二〇歳くらいの年齢ってそういうポーズを決めたがるから、そういう驕りみたいなことは許されないわけではないけれど・・・・・。
でも、それについてなんらかの形で意見する大人とか、それに反対する同じ世代の若者とか、そういう対立の中で揉まれていけばいいのです。けれど、全然揉まれないまま、本当にそれで「三〇歳になったら老人」のような感じでただただ、身過ぎ世過ぎで生きていく、ということになるのでは悲しすぎると思う。だからそこを少しだけ変える。何かちょっとした差なんだけれど、その差をうまく理解してください。


院長 高橋龍太郎著書 『人生にはしなくてもいいことがいっぱいある』より抜粋