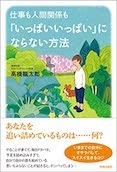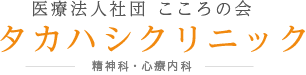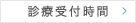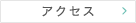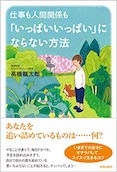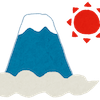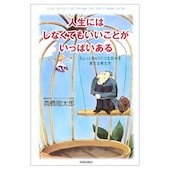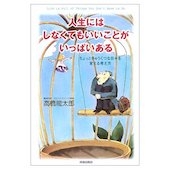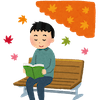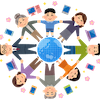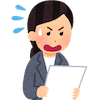思ようにならないとすぐにカリカリする、不機嫌になる、カッとなる、怒る、車を運転しているときなどもすぐにイライラする人、いますよね。
それは自己愛が強いせいなんです。精神的に未成熟ってこと。
優先順位をつけるのも段取りをつけるのもできるのですが、予定通りにコトが運ばなかったり、自分のペースを崩されてしまったように感じて余裕をなくしてしまうんですね。つまりエネルギー満杯状態で余裕をなくしている。
この手のタイプの人は、対人関係に問題が起こりやすいんです。コミュニケーション能力とイマジネーション能力が十分に発達していないから。やや発達障害かもしれないと思われる人も中にはいます。
人間が、成熟するということは、他人の立場や感情を理解できるということ。
すぐカリカリしてしまうのは性格的な要素もあると思うけれど、50過ぎたらもう変わりません。そう思ったほうがいいと思います。変わらない人のためにイライラしていたら、こっちがまいってしまいますから損ですよ。
実は昔はそういう男、たくさんいたんですよね。それでも、日本の女性は賢いので女性が寛大に受け入れていい子いい子していた、上手にコントロールしていたんです。最近の女性はそんな面倒なことはしません。お母さん役はしたがらない。自分も忙しいから面倒を見きれないんですよね。
こういう男性は、ダメ人間というわけではなくて、案外、自分のやるべき仕事や能力に秀でていることが多いから、社会的に破綻のないようにバランスをとっているんだよ、説明してあげることにしています。

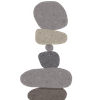

院長 高橋龍太郎著書『仕事も人間関係も「いっぱいいっぱい」にならない方法』より抜粋